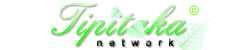
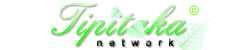

|
||
|
|
||
|
【仏教の新聞記事 • 日語版】 |
|
「大正大蔵経」データベース化. . . 7月完成、9月無料公開【読売新聞】 2007年5月8日,火曜日
大正時代から昭和にかけて編集された「大正新脩大蔵経」(大蔵出版)のデータベース化が今夏、完成する。 世界中の仏教研究者が使っている膨大な経典集を電子化し、利用しやすくするもので、13年余りかかった一大プロジェクト。責任者の下田 正弘・東京大学教授(インド哲学・仏教学)は「仏教研究における日本の大きな国際貢献だ」と話している。(泉田友紀) 大蔵経は仏教聖典の総称だ。各地に伝わる典籍を収集し、まとめる作業は6世紀ごろから、中国で盛んになった。版木を使って印刷された最 初の大蔵経は北宋の太祖による「勅版(ちょくはん)大蔵経」(10世紀末)とされる。以降、契丹版、朝鮮半島の高麗版などが作られてきた。 日本でも、奈良時代には書写や輸入が行われ、江戸時代には天台僧の天海、黄檗(おうばく)僧の鉄眼らが編んだ。こうした蓄積を踏まえ、 近代に編集されたのが大正新脩大蔵経で、後に文化勲章も受章したサンスクリット学者高楠順次郎氏らが、1924年から34年にかけて完成させた。 正編55巻、続編30巻、別巻15巻の全100巻。インド、中国、朝鮮、日本で編述され、用いられた仏典で構成され、「正法眼蔵」「歎 異抄」といった各宗派の典籍も数多く紹介する。収録範囲の広さ、整理された分類と使いやすさから、世界で最も優れた大蔵経とされている。 1990年代に入って、この膨大な仏典を研究者はもとより、一般の人にも手軽に触れてもらい、仏教の思想を広く伝えようと、テキストを インターネット上で公開する構想が研究者の間で持ち上がった。94年には「大蔵経テキストデータベース研究会(SAT)」が江島恵教・東京大学教授(イン ド哲学・仏教学)を中心に発足した。
100巻のうち、図像をのぞいた85巻を対象に、東大文学部内の一室を拠点に活動を開始。文科省の科学研究費を11年間で総額約3億円 獲得し、日本印度学仏教学会の支援を受けて研究会の委員らが学術チェックにあたった。98年には世界に先駆けて「大般若経」600巻を無料公開するなど、 大きな成果を上げたが、人件費や管理費などで膨大な経費がかかり、資金難で何度も頓挫しかけたという。 研究者に協力を呼びかける一方、江島教授が宗派の壁を超えて全国各地の寺を回り、住職らに意義を訴えるという“募 金行脚”を行ったことも。江島教授が99年に急死し、事業中断の危機に陥った後には、「仏教学術振興会」内に「大蔵経データベース化 支援募金会」を2000年に設置し、宗門や財界に広く支援の輪を広げてきた。この間、著作権の問題などから台湾の「中華電子仏典協会」からも協力の申し出 があり、ともに作業を進めてきた。 江島教授の没後、責任者を引きついだ下田教授は、「最初はこんな事業ができるわけがないと思っていたので、まだ夢の中にいるよう。事業 半ば、膨大な作業量に暗たんとする私を、『これは菩薩行なんだよ』となだめた江島さんの言葉を思い出します」と感慨深げに振り返る。 キーワード検索はむろん可能。大正新脩大蔵経の約3分の2の量にあたる韓国の「高麗大蔵経」やタイの「パーリ語聖典」がすでにデータ化 されており、日本版ができると、他の言語で書かれた仏典との比較対照も容易になる。また、仏教の思想や習慣が反映された「源氏物語」や「御伽草子」といっ た、文学作品の研究への寄与など、様々な可能性が期待されている。 特殊な漢字をチェックする校正の最終段階を経て、7月には完成する見込み。同月末に研究者らを招いて記念のシンポジウムを開く。9月に はネット上で無料公開する予定だ。 「日本の仏教界が宗派の枠を超え、経典を継承していくことの意味を理解して達成された貴重な事業で、“平成大蔵経 の開版”ともいえる。仏教の知恵の宝庫である経典の情報を多くの人と共有し、その豊かさを伝えていきたい」と、下田教授は意義を強調 している。 ウェブサイト: http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20070508nt0d.htm?from=os1 仏教新聞の特集記事 2008年11月16日,日曜日 2008年5月16日,金曜日 2008年1月25日,金曜日 |
娑界一覧 奈良県 法隆寺の「金堂壁画」 5月限定公開へ 初めて春の時期に実施 神奈川県 過去最多の来場者でにぎわう 横浜・陽光院、釈迦の生誕祝う「花まつり」 熊本県 能登半島地震 復興支援チャリティコンサート 熊本県 お釈迦様の誕生日を祝う「はぴしゃか花まつり」 娑婆の物語 中日交流の歴史たどる 黄檗宗開いた隠元禅師ゆかりの寺を訪ねて 佐賀県 佐賀市で花まつり 4年ぶりの稚児行列で釈迦の生誕祝う 三重県 高田本山専修寺で”東海地方最大級”のねはん図一般公開 宮城県 釈迦の誕生祝う「花まつり」 子どもたちが稚児行列を披露 愛知県 碧南の「釈迦三尊像」が国の重要文化財指定へ 広島県 本願寺派安芸教区の仏教婦人会連盟、10団体にダーナ募金 群馬県 安中・補陀寺 江戸期の涅槃図、掲げて徳たたえ 島根県 被災地を支援へ、14寺院がイベント企画 練香作り体験やカフェ 3月2日開催、松江 東京 NGO/NPOや仏教界などで活躍する人を応援する「アーユス賞授賞式」参加者募集 三重県 能登の被災地思い托鉢 三重の僧侶10人が6時間かけ20キロ 娑婆の物語 生命科学博士の住職、インドに旅立つ 釈迦時代の古代ハスを求める旅 東京 国宝11体の仏像が東京国立博物館に! 特別展「中尊寺金色堂」を見る 京都府 仏教美術研究上野記念財団が2024年度研究奨励金の受給者を募集 東京 全日本仏教会よりお知らせ「花まつりポスター」・「絵はがき」の頒布が始まりました 東京 駒澤大学大学院仏教学研究科公開講演会のお知らせ 福岡県 「世界遺産 大シルクロード展」 福岡アジア美術館で1月2日~3月24日 |
![]()
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Buddha sāsana.m cira.m ti.t.thatu.